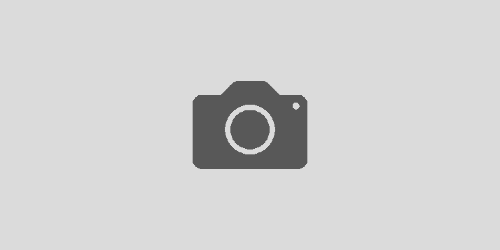その10 終末期医療について(2)
自分が死ぬ場所を選ぶことが出来るようになりました。その場所には、病院・施設・自宅などがあります。最期を自宅で迎えるがん患者さんを看取る医療を在宅ホスピスと呼んでいます。まだ一般的に広まっていませんが、一部では行われています。広がらない理由には、医療者側の課題も多いのですが、患者さんが希望されていても、家族の方々の理解が得られないことが挙げられます。
 患者さんは、自分の病名を知り、余命の少ないことに気付くと自宅に帰ることを望みます。医療者側も、がんの末期で症状のコントロールが少しでも安定している時期に、せめて一度は家に帰してあげたいと思いながら在宅での医療が始まります。しかし、これは医療者側に在宅ホスピスという選択肢がないと実現しません。また、肉親とはいえ自宅で末期の患者さんを世話することは、どんな事があっても最後まで自宅で看取るという強い意志が必要ですので、なかなか実行することは難しい事だと思います。
患者さんは、自分の病名を知り、余命の少ないことに気付くと自宅に帰ることを望みます。医療者側も、がんの末期で症状のコントロールが少しでも安定している時期に、せめて一度は家に帰してあげたいと思いながら在宅での医療が始まります。しかし、これは医療者側に在宅ホスピスという選択肢がないと実現しません。また、肉親とはいえ自宅で末期の患者さんを世話することは、どんな事があっても最後まで自宅で看取るという強い意志が必要ですので、なかなか実行することは難しい事だと思います。
このように書かれると、とても難しそうで、私たちには出来そうもないと思われるかもしれませんが、それ程でもないと思います。本当に大変なのは臨死期という約一週間前後の期間です。この間、主介護者が1名とその方を支えてくれる2~3名の方がいて、協力して頑張れば可能です。
それでは、実際に在宅ホスピスを行った症例について紹介します。この患者さんは、膀胱がんで骨転移のある方です。年齢は77歳の女性です。甲府市内の総合病院を退院されて、私どもの訪問看護ステーションに在宅支援の依頼がありました。訪問しているうちに、患者さんは経口摂取ができなくなり、また疼痛も増強したので在宅医療を行うようになりました。介護者は主にお嫁さんと東京在住のお姉さんで、夜はご主人達も交代で看ていたようです。
ご本人は、モルヒネの服用により痛みが軽減し、食欲も少しでてきました。ある時、東京のお姉さんから、患者さんとハワイへ行きたいというお話がありました。自宅へ帰ってきた大きな理由は本人がお孫さんとハワイでステーキを食べることが人生最後の望みだというのです。私は、思わず驚いて大きな声で、「えー、ハワイですか?」と答えながら、頭の中でもっと早い時期なら良かったのに、遅すぎないかなとか、ワイキキビーチでステーキを食べている患者さんの姿を思い浮かべましたが、その時には何とも答えられませんでした。
時間が限られていましたので、私がOKを出しますと、準備はどんどん進められていきました。そして約一週間の旅行に出発しました。その時の患者さんは、わずかですが経口摂取し、痛みもコントロールされていましたが、無事に帰れるかと内心、心配しておりました。しかし、成田に無事に着いたという一報を聞いてとても安堵したことを覚えています。旅行中、昼夜逆転し家族は困ったようですが、移動中は問題なく、ステーキも少し食べたとのお話でした。
東京で一泊されて山梨に帰ってきたという連絡を頂いてお宅に伺うと、本人から「ただいま」という言葉を聞いてとても嬉しかったです。しかし、体力の消耗が著しかったので点滴のために一日入院をしてもらいました。この頃から殆んど昏睡状態になり、帰国してから一週間後自宅で最期を迎えました。この方の看取りから、人間には素晴らしい力が秘められていて、希望を持てば、不可能と思われることでも可能にする力を、人は持っているとつくづく感じました。
最期を迎える場所に自宅を選んだ人々は、みなさんとても穏やかな顔をして、家族に囲まれて最期を迎えています。がんの人に限らず終末期を迎えた人もご自宅で最期を迎えることが出来る時が来ると良いですね。